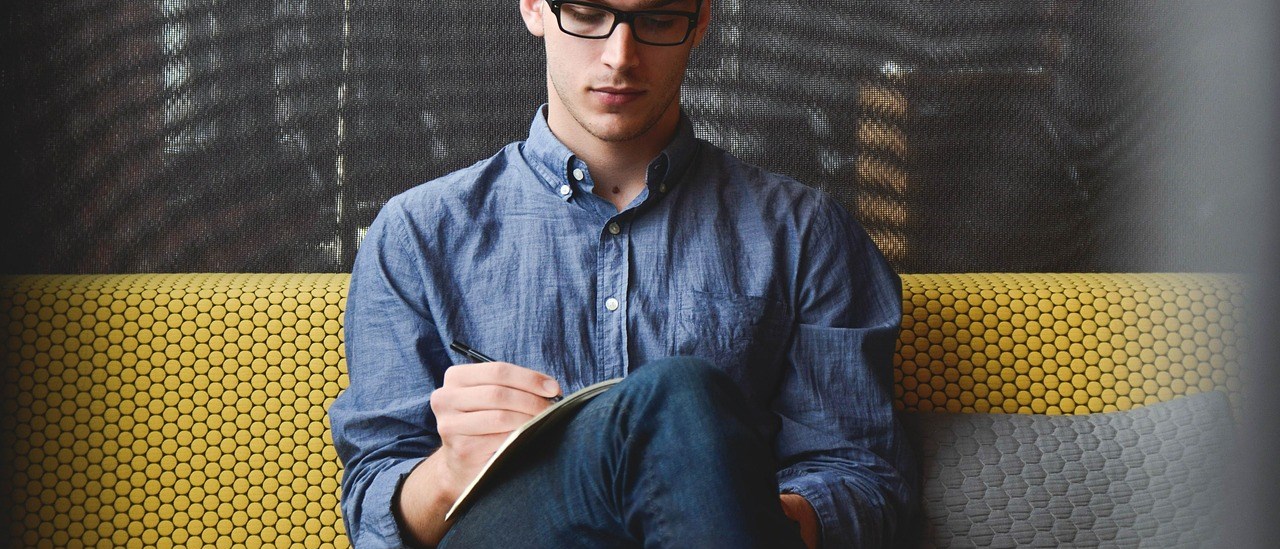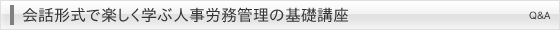
木戸部長は、「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、「36協定」という)の締結に向けて書類の準備をしている。例年、前年の書類を見ながら作成しているが、記載する項目が何を意味しているのか疑問に思い、社労士に確認することにした。

今、来年度の36協定の締結に向けて、書類を作成しています。例年、前年のものを参考に作成しているのですが、ふと、いくつかの項目について何を記載するのか疑問に思ったので、それについて教えてください。

わかりました。

一つ目は、36協定の協定事項とされている「労働者数」についてです。これは、時間外労働・休日労働を行わせることが想定される人数だと理解していますが、いつの時点の人数を記載すればよいのでしょうか。

貴社の場合、36協定の起算日が2026年4月1日となっていますので、4月1日時点の人数を記載することになります。入退社があると思いますので、それも加味した人数になりますね。

なるほど。3月で退職する人や4月1日付で入社してくる人がいますので、それを加味した人数で記載したいと思います。
次に、「延長することができる時間」について確認させてください。「1日」、「1箇月」、「1年」という区分があり、当社ではこの1日のところは、以前から4時間と記載しています。通常ではこの4時間の範囲内に収まっていますが、機械の突発な故障などが発生した場合には、残って対応する従業員も出ることになり、4時間を超える可能性があると思います。

確かに、突発的なことが発生した場合は、4時間を超えるということも考えられますね。

もし4時間を超えて労働させてしまった場合はどのようになるのでしょうか?

この場合、36協定違反になりますね。
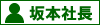
月45時間、年間360時間は遵守するように意識していますが、1日のところに記載する時間数も、当然ながら遵守が必要ということですね。

その通りです。書類に記載した内容は、全部守らなければならないことを理解した上で、実態に合うように中身を検討してもらう必要があります。

なるほど。確認したかった項目はこの2点ですが、これ以外によく誤解されている項目等がありますか?

休日労働に関する項目に注意が必要です。協定事項には「労働させることができる休日の日数」があり、36協定届には「労働させることができる法定休日の日数」があります。
「労働させることができる法定休日の日数」とは、法定休日に労働させる可能性のある日数をいいます。厚生労働省が公開しているリーフレット「36協定の適正な締結」にある36協定届の記載例では、「1か月に1日」という内容になっていますが、この場合、法定休日に労働させることができるのは1ヶ月に1日のみとなります。

そのような意味になるのですね。繁忙期に法定休日のうち、2日は出勤してもらう可能性がある場合は、「1か月に2日」と記載するということですね。

そうです。併せて、この法定休日に関連して、「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」を記載することになっていますが、これは法定休日に労働させる場合の始業時刻と終業時刻をいいます。
この時刻について、会社の通常の始業時刻と終業時刻を記載しているケースを見かけますが、この時刻が法定休日に労働させることのできる始業時刻と終業時刻となります。

そのような意味だったのですね。

通常の始業時刻よりも早く出勤させる可能性がある場合などは、会社が想定する時刻を記載することになりますね。

今日の話をもとに、書類を作成してみます。
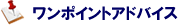
36協定に特別条項を盛り込む際に、特に気をつけたい項目としては「限度時間を超えて労働させる場合における手続き」があります。この手続きの方法は任意ですが、例えば「過半数代表者への申し入れ」と記載した場合は、実際に特別条項を適用する際、会社は従業員の過半数代表者へ事前に書面等で申し入れを行う必要があります。さらには、申し入れを行ったことの記録を残す必要があります。どのような方法を用いることが適当かは検討の上、記載するようにしましょう。
■参考リンク
厚生労働省「36協定の適正な締結」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
- 従業員の健康情報を取り扱う際の注意点2026/01/08
- 人事労務に関する書類(データ)の保存期間2025/12/11
- 営業所を開設した際の安全衛生管理体制の考え方2025/11/13
- 自社が副業先となる場合の労務管理上の注意点2025/10/09
- 支払賃金が最低賃金以上となっているかの確認方法2025/09/11
- 賃金台帳の備え付け義務とは2025/08/14
- 業務災害で従業員が休業する際の待期期間の考え方2025/07/10
- 通勤手当の支給額や労災保険の適用に関する考え方2025/06/12
- 改めて確認したい無期転換申込権の発生と特例の取扱い2025/05/08
- 出張旅費規程を見直す際のポイント2025/04/10
- 仕事と介護の両立支援制度を利用する際の家族の要介護状態の判断2025/03/13